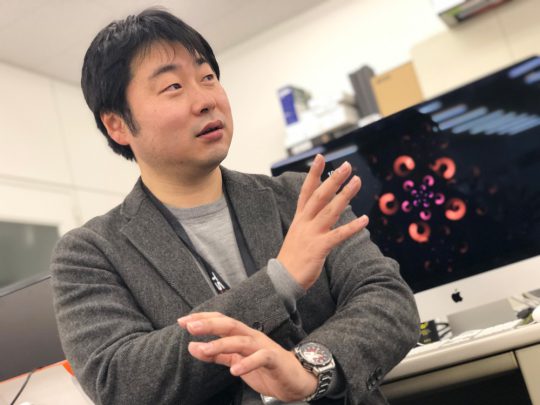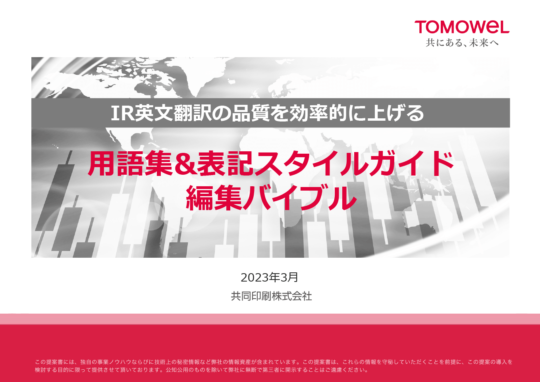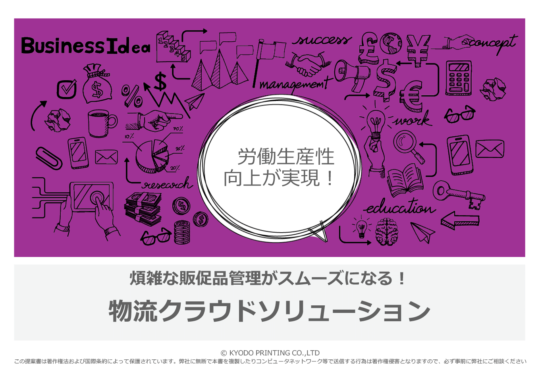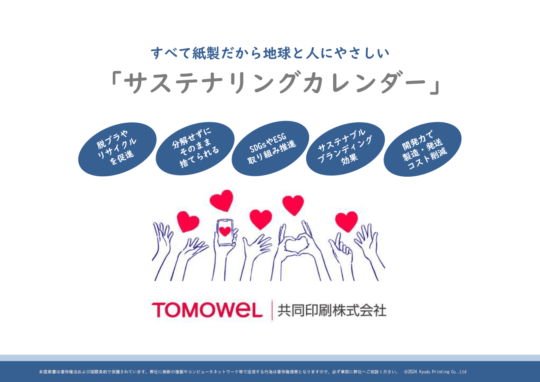動画がマーケティングや広告で重要な役割を果すようになっているのがここ数年の傾向です。しかし、その動画が編集されたものではなく、どんどんリアルタイム化 = LIVE映像として配信されています。
主要SNSはそれぞれにライブ配信機能を備え、ユーザー同士はもちろん、企業とユーザーの動画コミュニケーションにもリアルタイム化の波は押し寄せています。
各SNSのLIVEコンテンツ活用ケース
Youtubeやニコニコ動画、ツイットキャスティングのような、動画配信を主とするプラットフォームだけでなく、Facebook、Instagram、Twitter、LINEの主要SNSもLIVE配信機能を強化しています。
InstagramやLINEはLIVEを閲覧するためには事前にフォローや友達登録が必要となっており、フォロワーの獲得に向けたキーコンテンツとしてLIVE動画を活用するケースも増えています。
また、Facebookではユーザーのビジネス色を活かし、セミナーやカンファレンス、プレス発表などをリアルタイムで配信する事例があります。
近年のユーザーのWeb利用ニーズにおける、情報の速さで優れるSNSを検索サイトよりも重用する傾向を考慮すると、SNSでのLIVE配信はユーザーニーズとマッチしたコンテンツ形式と言えそうです。
人気を集めるLIVE配信アプリ
上記のようなSNS系の動画配信機能のほか、動画配信アプリにも注目が集まっています。ここでは最近利用されているアプリのいくつかをご紹介します。
- ●LiveMe
LIVE配信中に、ユーザー同士がチャットすることが可能。コインを購入し、お気に入りの配信者にアプリを通じてプレゼントを贈ることもできます。
LiveMe
- ●17 Live
世界9か国で展開している台湾発のLIVE配信アプリ。全世界に4,000万人以上のユーザーを擁しています。歌手やモデルとして活躍中のユーザーからの配信もあり、盛り上がりを見せています。
17 Live
- ●JAMLIVE
他のLIVE配信アプリとは一味異なるアプリ。ユーザーはライブクイズショーに招待され、賞金獲得を目指す仕組みになっています。
JAMLIVE
- ●SHOWROOM
アイドルやアーティスト、声優、お笑い、スポーツなどの配信が視聴できるアプリ。アプリのダウンロードページではこうした視聴の仕組みが「仮想ライブ空間」と表現されています。
SHOWROOM
LIVE配信のメリットとは?
いま動画マーケティングでも重要な役割を担うようになっている点は冒頭でも述べた通りですが、編集された動画に対してLIVEコンテンツの配信メリットをご紹介します。
動画を編集する手間が不要
膨大なコンテンツの中から、自社のものをユーザーに選んでもらうには高いクオリティ、話題性は欠かせません。一方で、コンテンツの質を高めるために動画であれば撮影・編集などに多くのリソースを必要とします。
しかし、LIVE配信であれば撮影や編集のための時間は必要ありません。ライブ感と配信を通したユーザーとのリアルタイムコミュニケーションが武器となります。直接の対話を通じて、ユーザーのエンゲージメントを高めることができます。
信頼性が高い
動画を編集できないということは、すなわち生の姿を届けられるということです。視聴者のほうでも、編集されていない動画であることがわかっているため、スクリーンに映し出されるものを「真の姿」と捉えます。そのため、視聴者(ユーザー)からの信頼性の高いコンテンツとなり、その信頼性ゆえに「見てみよう」という気持ちも高まるでしょう。
ブランドに対する親近感の獲得
完成されたコンテンツとしてユーザーに提供される通常の動画と異なり、LIVEコンテンツはリアルタイムの出来事を企業とユーザーが共有し、一体感が生まれます。そのため、ユーザーからブランドへの親近感の獲得という面で、LIVEコンテンツは通常の動画より優れていると言えます。
コストを抑えられる
例えば、講演会、セミナー、ショーなどの様子をLIVE配信すれば、各地に遠征してこうしたイベントを何度も行うよりも、コストが抑えられます。もちろん、LIVE配信時に収録した動画を後日コンテンツとして再利用することもでき、その際にLIVE配信時のユーザーの反応を伝えられるなど、低予算で効率的なマーケティングを可能にします。
興味の度合いが強いユーザーに見てもらえる
LIVE配信は基本的に強制視聴ではないため、もともとの興味の度合いが強いユーザーに見てもらえるという利点があります。興味の度合いが強ければ、LIVE配信時のコミットメントも深くなる可能性が高く、効果的なマーケティング施策の1つになり得ます。
LIVE配信のデメリットにも注意
多くのメリットが見込めるLIVE配信ですが、デメリットにも注意したいものです。
LIVE配信のメリットの1つとして「編集をしなくてよい」ことが挙げられますが、これは裏を返せば、「編集できない」ということで、その点はデメリットとなります。したがって、LIVE配信時に余計なものが映らないか、シナリオに好ましくない表現が入っていないかなど、事前に細かな部分のチェックが必要です。
ただし、たとえ完璧なシナリオを用意したつもりでも、視聴者の反応によっては、少しアレンジしたほうがよいこともあるかもしれません。そうした際にフレキシブルに対応できるよう視聴者の反応パターンをいくつか想定し、ある程度シナリオに幅を持たせておくと、なおよいでしょう。
LIVE配信のマーケティング活用ケース
モバイルでの通信環境が整ってきた今、LIVE配信をマーケティングに活用する企業が増えています。例えば、以下のようなLIVE配信をマーケティングに利用することができるでしょう。
- ●イベント(ライブ、ファッションショーなど)
音楽のライブや、ファッションブランドのランウェイショーといったイベントの様子を配信。こうした華やかなイベントの生配信には「ライブを見られるチャンスは一度だけ」という価値が生まれます。
- ●舞台裏(イベント、企業活動などの)
イベントを行う際の準備や企業活動の裏側など、普段ユーザーが目にすることのないものを見せることで、ユーザーとの距離を縮めます。
- ●インタビュー
自社製品を使用しているタレント、モデルなどへのインタビューを配信。企業やブランドの姿をより具体的にユーザーに伝えることができます。録画した動画を配信することもできますが、「○月○日LIVE配信!」とすることで、よりユーザーの期待感を高められます。
- ●講演会・勉強会
講演会や勉強会も事前に録画したものを配信することができますが、LIVE配信にすることで、視聴者からの質問をその場で受け付けたりすることもでき、よりコミットメントの度合いを深めることが可能です。
- ●商品の発表、イベントの告知など
新製品の発表や催事の告知といった「アナウンス」は、LIVE配信することで意気込みや熱意を伝えやすくなるでしょう。
LIVE配信のマーケティング活用事例
それでは、実際にLIVE 配信をマーケティングに活用している企業の事例を2件ご紹介します。
シボレー
シボレーは全EV(電気自動車)の 2017 Bolt EV発売に際し、CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)2016におけるスピーチの様子をLIVE配信しました。その内容は、電気自動車のニーズや将来性を消費者に伝え、電気自動車に対する不安を払拭するものでした。こうしたストーリーをCESの参加者だけでなく、他の人々にも広く配信することは、幅広い層からのブランドへの信頼獲得につながります。
LIVE配信に使用されたプラットフォームはFacebookです。この配信をきっかけに、「僕が今まで所有した車の中では○○が一番だな」、「コルベットのEV版が登場したら買うよ」といった会話がユーザーの間で生まれ、商品への関心が高まっています。
バーバリー
近年デジタルマーケティングに注力するバーバリー。業界初のファッションショーの3D LIVE配信を行うなど最新の技術をマーケティング施策に取り入れており、ランウェイに登場したアイテムを、ファッションショーのLIVE配信直後から一部の店舗・オンラインストアで購入できるシステムも導入しています。ライブでファンのエンゲージメントを深め、その熱い気持ちが冷めやらぬうちに購入可能とすることで、販売機会を逃さず、次回のライブへの興味も高められるなど、多くのメリットが得られるでしょう。
動画コンテンツが主流になればなるほど、“動画内での手法の細分化”は今後も進んで行くことが予想されます。まずは他者のLIVEコンテンツの活用状況をリサーチするところからスタートしてはいかがでしょうか?

 2019.03.08]
2019.03.08]